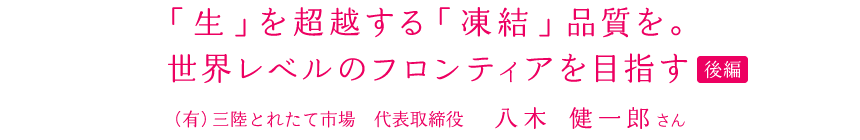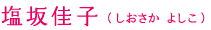震災を機にリ・スタート。イチから創り変える覚悟
岩手県南部の太平洋沿岸に位置し、最大被災地のひとつとなった大船渡市。八木さんも周りの漁業者たちも、多くのものを失った。
![[photo04]](../imgs/interview/vol15/photo04.jpg)
![[photo05]](../imgs/interview/vol15/photo05.jpg)
「本当に全部流されて。日常とはこれほどまでに薄氷だったのか、とあの時はいろいろと考えましたね。でも、会社に関していえば、流されたのは施設だけで、次の時代が求めるであろうグランドデザインは、これまでの経験からおおよそ見えていた。だから、被災して失ったものを復旧させるのではなく、お客様から寄せられていた本質的な課題を解決する、新しい生産基盤を生産者とイチから創生しなおす絶好の機会だと思いました」
漁業の新しい姿を構築する為、社内外、さまざまな場所へ相談に出かけた。すると、八木さんの情熱と心意気をかってくれたCAS(キャス)の製造元が、復興支援という名目のもと、実験機を貸与してくれることになった。細胞に障害を与えることなく凍結することができ、再生医療にも使われるという最新の冷凍技術CAS。購入すれば数千万円という最高レベルの凍結機械だ。
![[photo06]](../imgs/interview/vol15/photo06.jpg)
「とれたて」よりもおいしく、素材は操縦できる
しかし、最新鋭の機械を手に入れながらも、八木さんたちの「生に勝るものはない」という思い込みは根強く、生魚を販売しながら、CASを使っては実験だけを繰り返す日々。
「どういうアプローチをすればいいのか全くわからなかったんです。冷凍して解凍する。その結果、生に極めて近い鮮度の魚が出現する。お客様からは『解凍する手間が余計にかかるだけだから、扱い慣れている生の方がいい』と言われ、ぐうの音も出ない状況が続きました(笑)」
それが、約5年間も続いたという。
「生屋でもない、冷凍屋でもない、どっちつかずの中途半端な状態に猛烈に苦しんで。結局は、僕が経営者として『選択と集中』ができていないんだな、と。それである時、思い切って、鮮魚販売からは完全に撤退する!と宣言したんです」
社内では、数千万円の売上があった「生」をやめ、たいして売れてもいない「冷凍」をとるなんてとんでもないと全員が猛反発。しかし、今後「生」が伸びていくビジョンが全くみえなかったという八木さんは「今、凍結に舵を切らなければ手遅れになる」と強制的に押し通したのだ。いよいよ、三陸とれたて市場の冷食に対する本気の挑戦が始まった。
凍結に鮮度を求めるなど、当時は手本にするべきものも無ければゴールも定かではない。自分たちが作ったものが、本当に価値があるのかもわからない……。
そこで八木さんは、付き合いがあった東京の有名ホテルに協力をあおぎ、冷凍したものを送ってテストしてもらい、フィードバックをもらい始めた。最初はホタテなどから始め、しだいに魚を送ってみる。と、「血が回っている」「処理が甘い」と衝撃的な言葉が返ってきた。「海から獲ったばかりの魚を迅速に凍結して直送しているというのに、いったい何が悪いの?って、当時の僕らにはその意味すら分かりませんでした」
![[photo07]](../imgs/interview/vol15/photo07.jpg)
![[photo08]](../imgs/interview/vol15/photo08.jpg)
すると、ちょうどその頃、隣接する宮城県の石巻市で「神経締め」を導入した若手漁業者たちが話題になり始めていた。八木さんは知人のつてをたどって指導に来てくれるよう頼み、周りの漁業者を集めて技術を学ぶ機会を設けた。
「当初、地元の人たちは批判的でした。自分たちが絶対的に良いものを食べている自信があったので、『そんな技法は手間が掛かるだけ。消費地側で少しでも魚を傷ませないようにする、負け惜しみのような技術だろ』って。実は僕も、最初はその価値に気がついてはいなかったんです。でも実際にそういう処理をした素材を扱ってみると、自分がテッペンだと思っていたものは全然テッペンじゃなくて、ただの原石だった。原石は磨けば磨くほどに、輝きが増すということがわかったのです」
![[photo09]](../imgs/interview/vol15/photo09.jpg)
水産と医学。蓄えられていた知識が直結
なぜ獲った魚が獲ったとき以上においしくなるのか。その仕組みを調べていくうちに、八木さんはまた子どもの頃のことを思い出していた。祖父母の家に帰省した際、絵がたくさん載っていたので興味を持ち、持ち帰って読みふけった解剖学や法医学の教科書。 「頭の端っこにあったガラクタのような情報と、神経締めがガチッとつながったんです。アレ? 僕この知識、持っているぞ。大学時代に勉強していた生理学の知識もそのまま使えるじゃん!って。」
そこからスタッフ総動員で、原石を磨き上げる研究のような日々が始まった。
「活〆、脱血、熟成、凍結などの最適化作業を、ひたすら繰り返しました。思い通りの品質が作れない場合は、その要因がどの工程の何に起因しているのか。研究が進むにつれ、それまで断片的だった情報が徐々につながり、因果関係がみえてきた。そうして2年が経った頃、商品の多くは美しい透明度を持ち、安定して量産できるようになったのです。まさしく、素材である原石と生産手技、CASとが『人馬一体』のように機能し始め、素材を操れる感覚が現場に浸透した時でした」
![[photo10]](../imgs/interview/vol15/photo10.jpg)
たとえば、素人目にも新鮮と分かる、獲れたばかりの透明なイカ。そのまま食べると固くて味もしないため、漁業者などは、わざと数日間置いて白くし、甘さを引き出してから食べるという。
「活イカという原石に、タイミングよく〆や下処理、凍結熟成などの磨きの工程を与えると、透明な見た目と歯ごたえは『活』の様でいて、甘さのあるイカを作ることができるんです」と八木さん。「さらに、イカの透明度は電池のよう。フル充電時は透明で、電池がなくなるにつれだんだんと白濁していくことから、細胞のバッテリ(ATP)残量の指標としてみることができます。鮮度が劣化する要因である処理工程の不都合個所を容易に特定でき、イカの品質を操れるようになると、それと同じ考え方を用いて、ほかの多くの魚も品質向上を果せるというメリットを発見しました」
さらに「使い切りサイズで刺身を凍結してほしい」という顧客の要望に応えるため、三陸とれたて市場では、移植医療の現場を参考に生産の動線を組んだというから驚く。
「皮をはがれて脆弱になった魚の身をどうやって外界から守り、『活』の機能を代替回復させるか。こうした弊社のモノ創りは命を扱う医療の仕事と、どこか似ています。だからうちの会社は水産加工というより、イメージとしては血液センターに近い形に発展を遂げました(笑)」
![[photo11]](../imgs/interview/vol15/photo11.jpg)
![[photo12]](../imgs/interview/vol15/photo12.jpg)
![[photo13]](../imgs/interview/vol15/photo13.png)
およそ20年前、運命に引きずり込まれるように「イヤイヤ」水産の世界に入った八木青年。彼が仲間たちと立ち上げた『三陸とれたて市場』は今、世界中の常識を覆そうとしている。
三陸とれたて市場
https://www.sanrikutoretate.com八木 健一郎(やぎ けんいちろう)
1977年静岡県生まれ。北里大学水産学部(現・海洋生命科学部)卒業。2001年に地元の商店と協働して鮮魚のネット販売を始め、2004年有限会社三陸とれたて市場を設立。船に設置したネットカメラで漁を中継するなど、ICTを活用した販促を行う。東日本大震災後は、地元の漁業者とともに漁業復興に取り組み、魚の加工プラントを新設。地域の雇用創出に貢献するとともに、競争力のある商品開発を行っている